【アウトプット】【プレゼンテーション】私が実践した、自身の考えをまとめて発信する際に必要な思考方法
こんにちは
今回は物事をアウトプットする際に私が心掛けていることについて書いていきます。
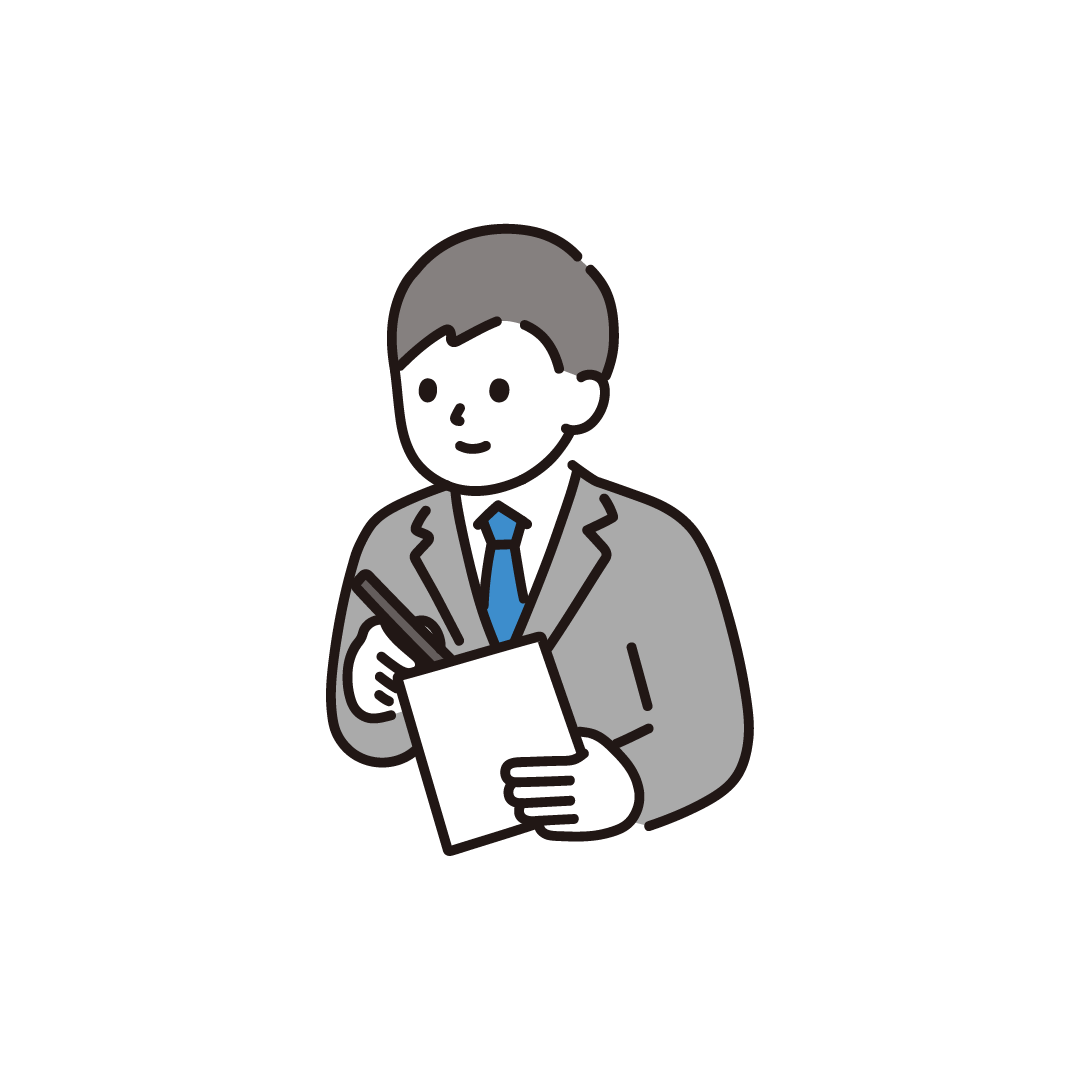
学生の場合は授業や試験・研究活動、社会人であれば上司への報告から稟議まで様々な場面でプレゼンテーションを行う機会がありますし、そのタイミングで行っていることはまさしく「アウトプット」に他なりません。
ここまで書いて気づいた方も多いと思いますが、「アウトプット」のタイミングで我々は他者から「評価」されています。
このブログの内容も例にもれず「アウトプット」であり「読者」という他者から「評価」されています。
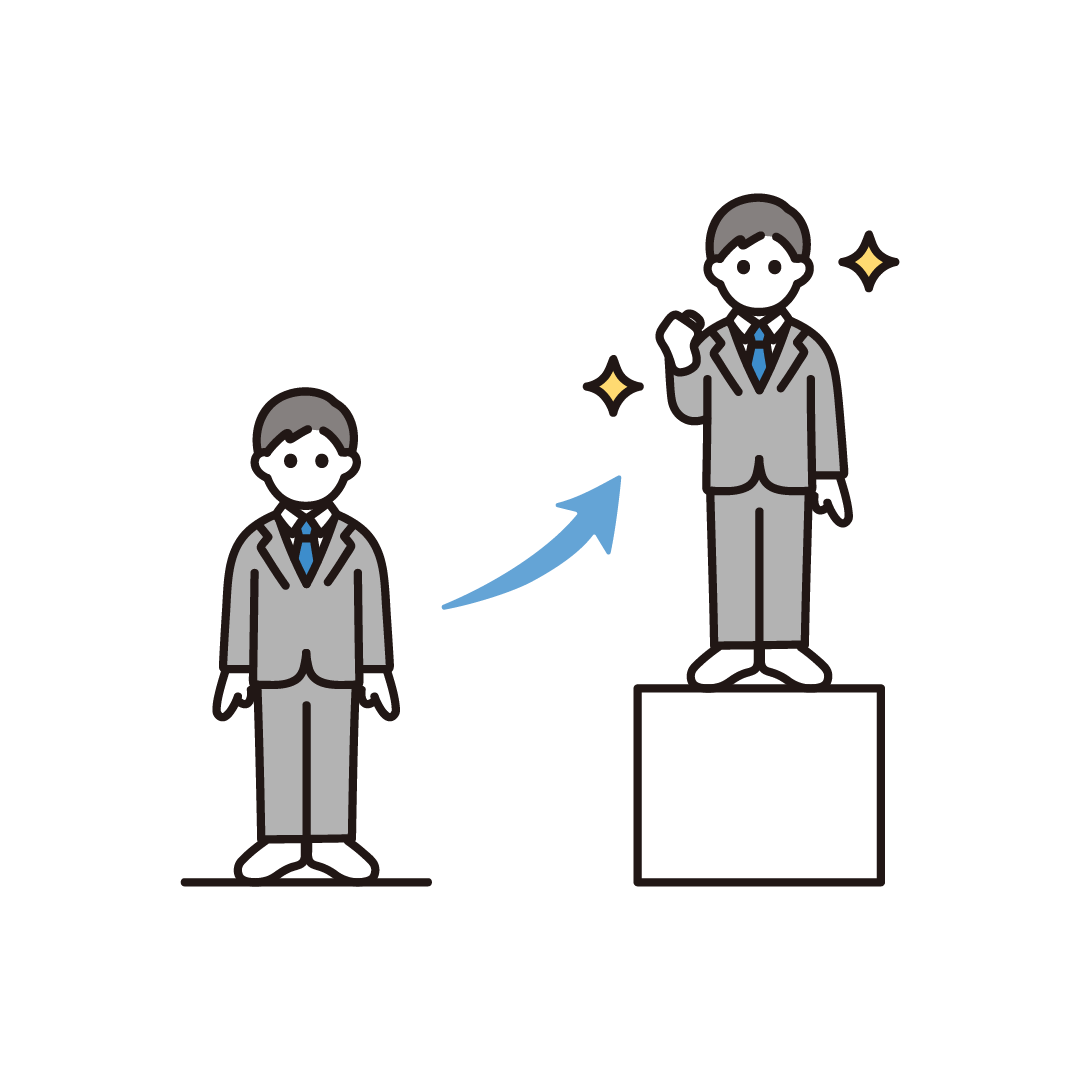
つまりアウトプットを制する者はこの競争社会を制することが出来ると言っても過言ではないのです。
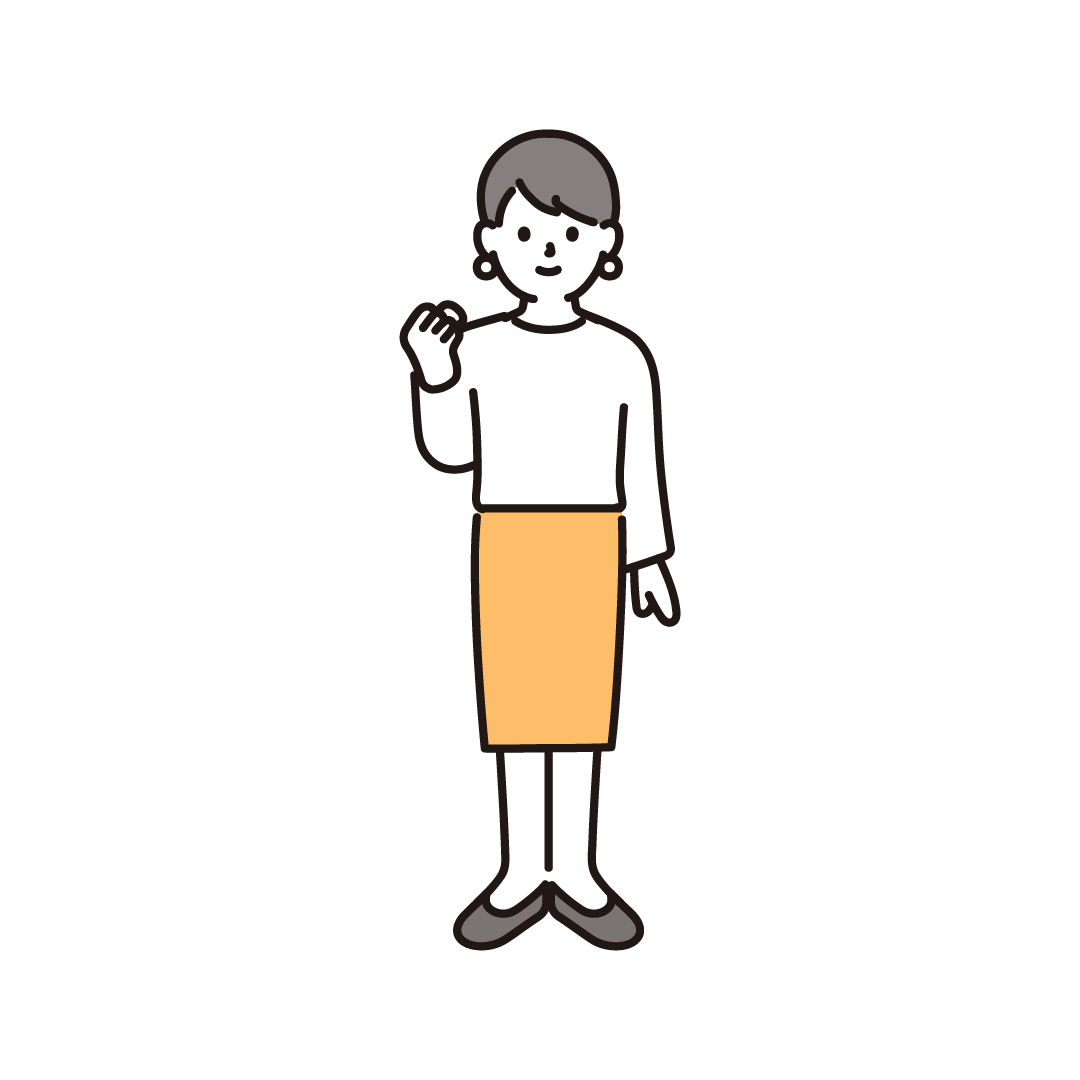
この記事を読むと現代社会を生き抜くためのヒントが得られるかもしれませんし、どこかにあるそれぞれにとってのヒント・エッセンスを持ち帰ってほしいです。
結論
アウトプットの質を向上させる方法は、「結論から考える」です。
至極当たり前です。
ですが多くの人はできていないですし、私自身もできていないことが多いです。
アウトプットが上手くいった、と感じる時は大抵、結論が定まっていてその解像度・理解度が高いという体感があります。
では具体的に、どのように結論からアウトプットを考えるのかについて、実践している方法を記載します。
詳細
結論を決める
最初に説明したように、結論から決めましょう。
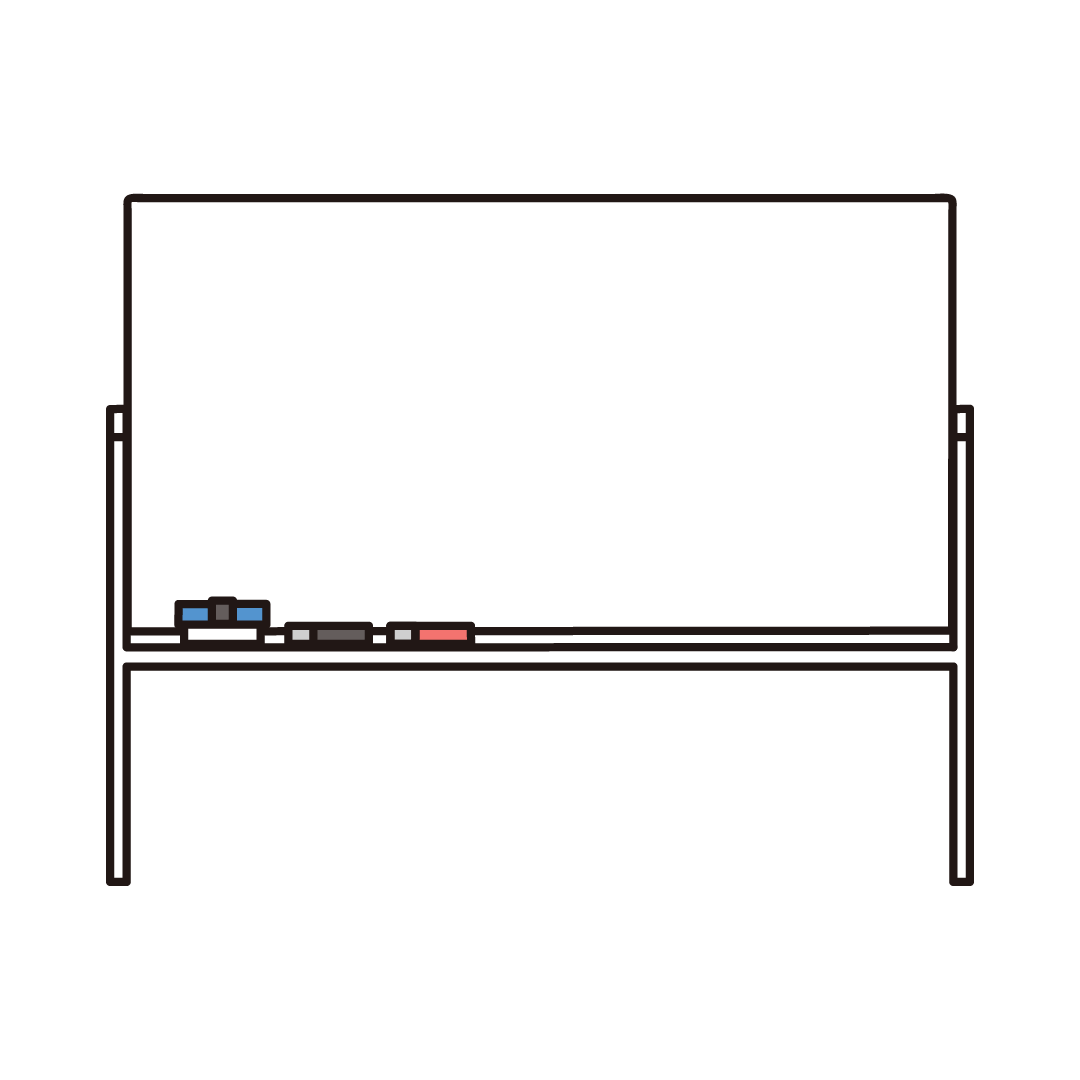
成果物を作成する段階で多くの時間をかけて調査を行うはずです。
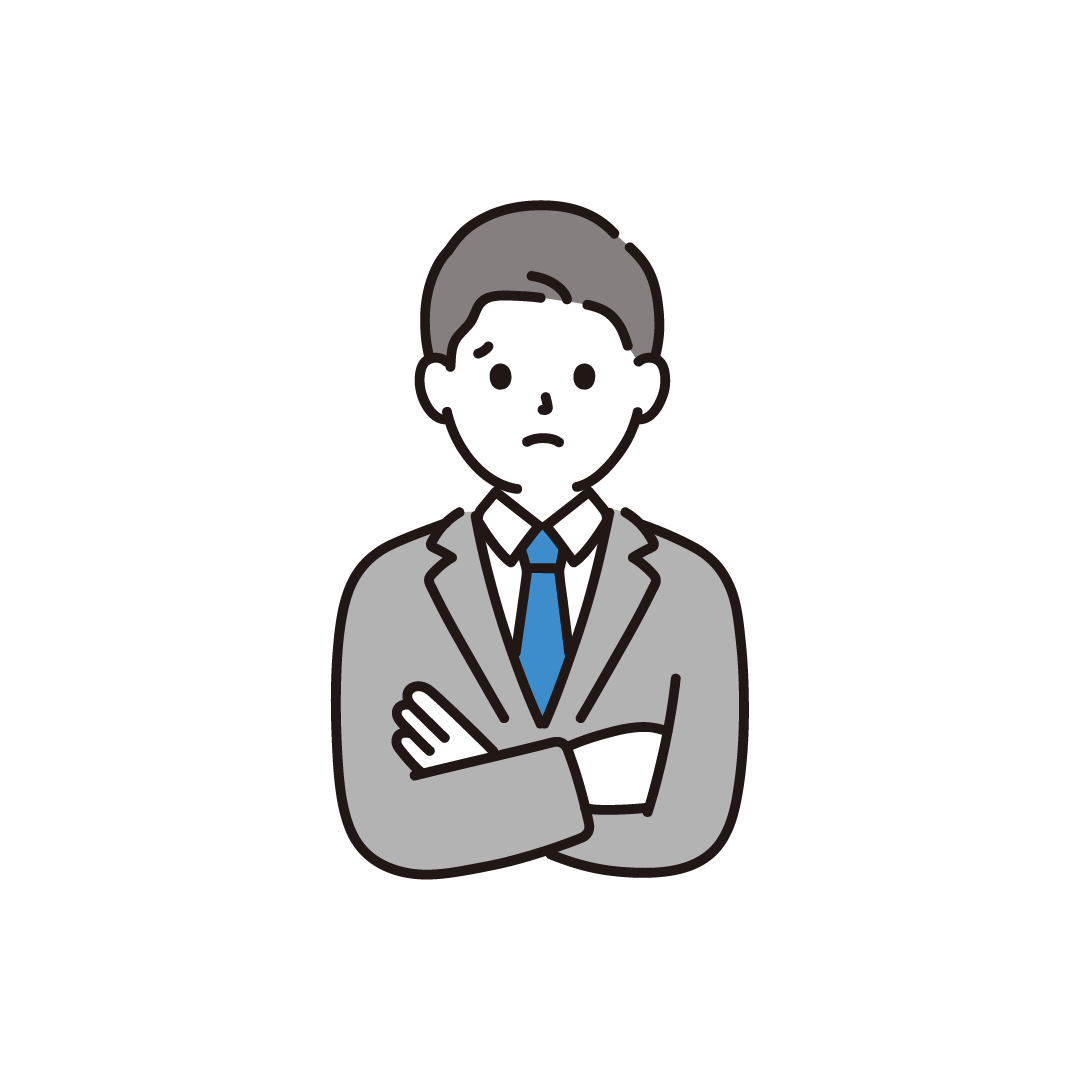
調査等を行う際には結論を考えながら探すということが必要となってきます。
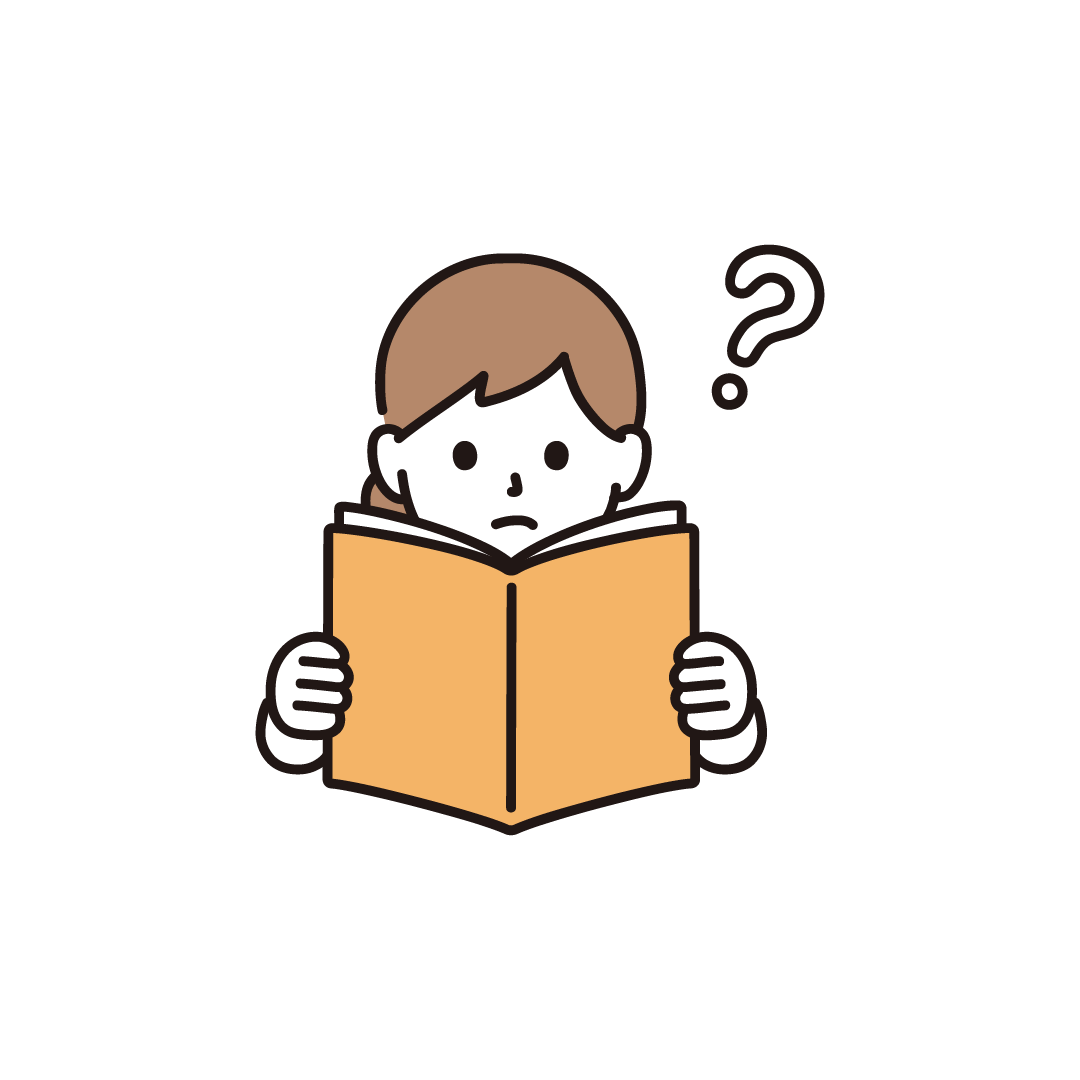
仮説で良いので結論を設定し必要な情報を集めていくことで、一貫した論理を持って納得感のあるアウトプットが出せるはずです。
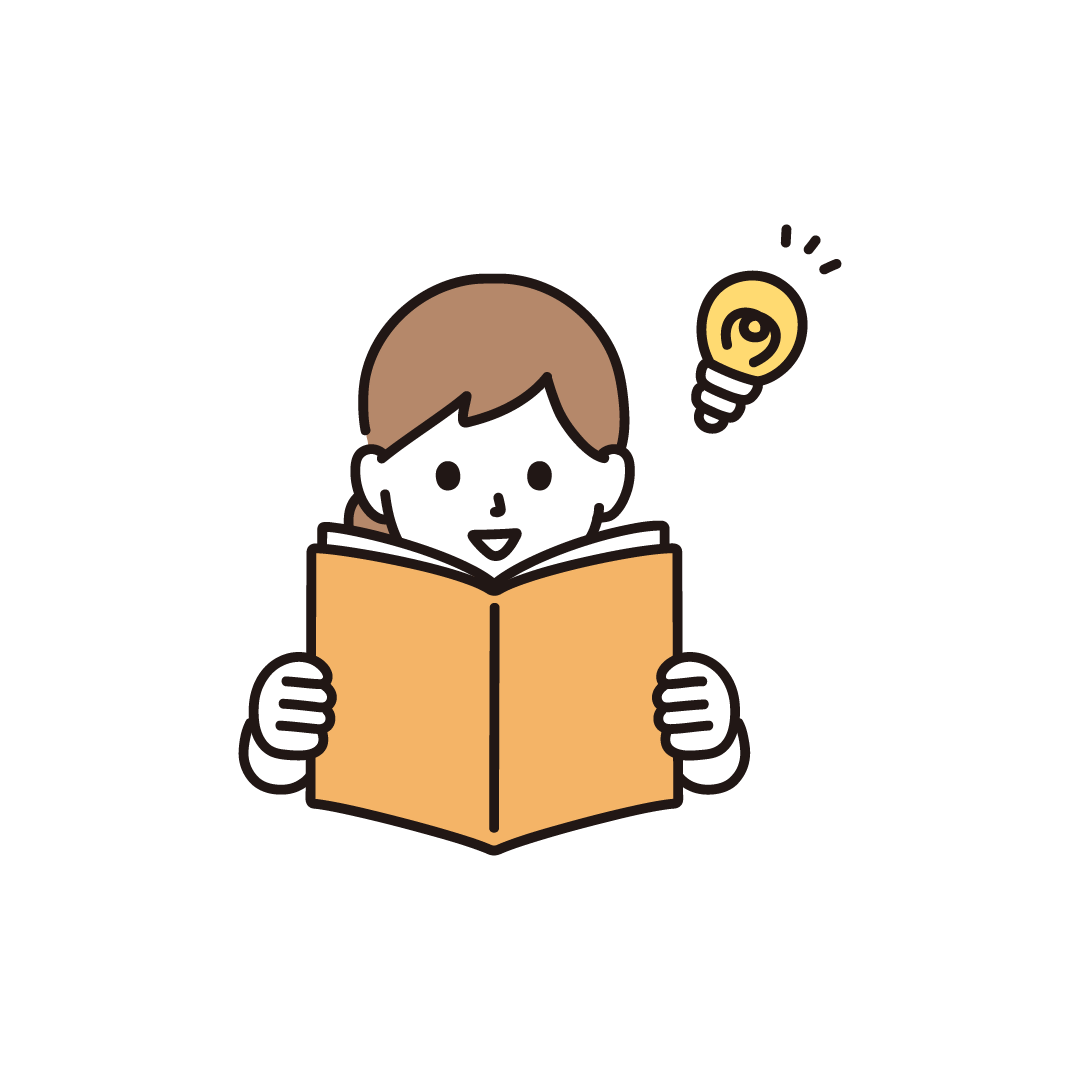
勿論、結論に関係ない部分に関する調査に抜け漏れが発生することは容易に考えられます。
しかし、目的が「調査」ではなく「主張」や「説得」なのであれば、そのための結論に関わらない部分の調査は思い切って行わないという選択が必要になるでしょう。
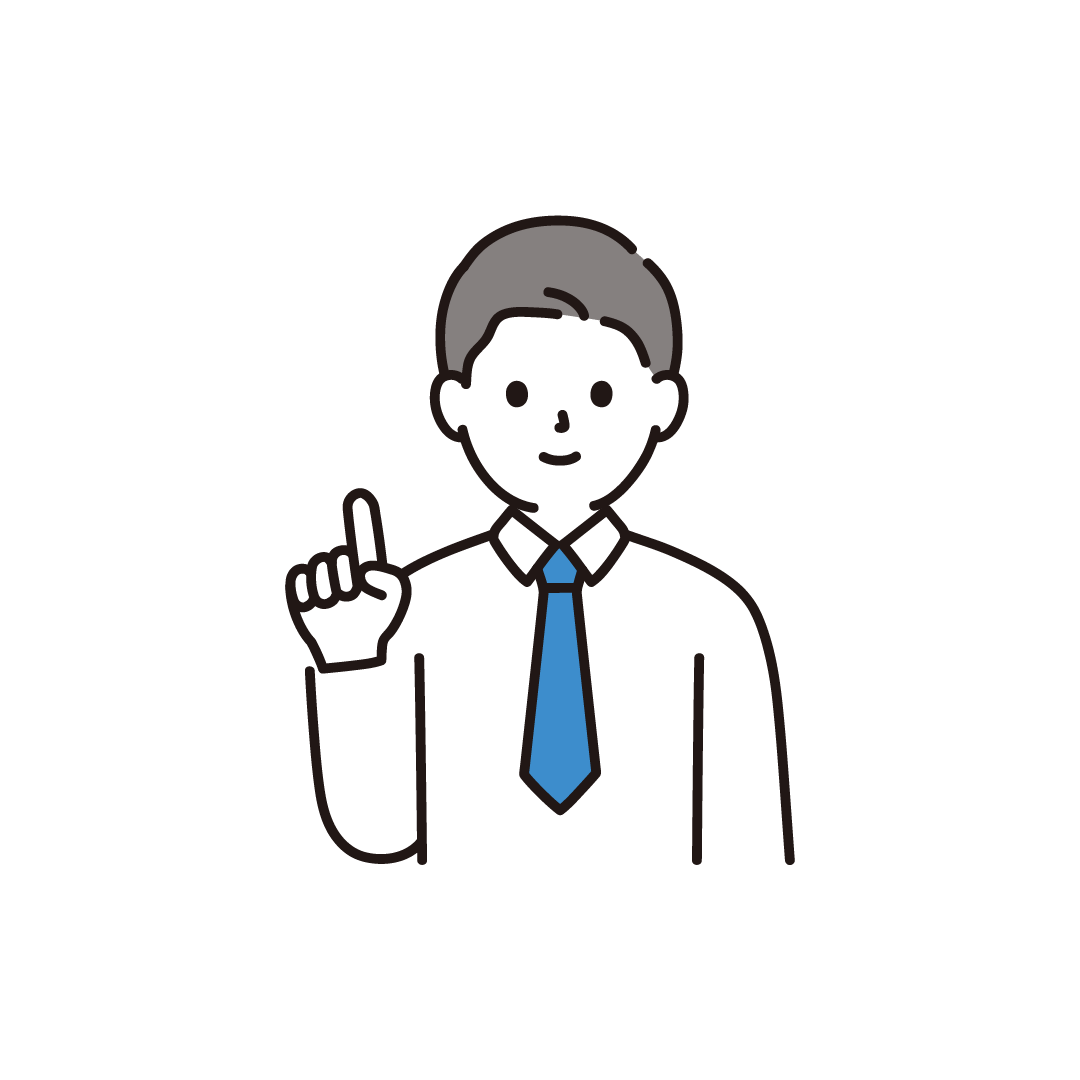
アウトラインから作る
アウトプットはアウトラインから作りましょう。
これは「結論から考える」を補足する考え方になります。
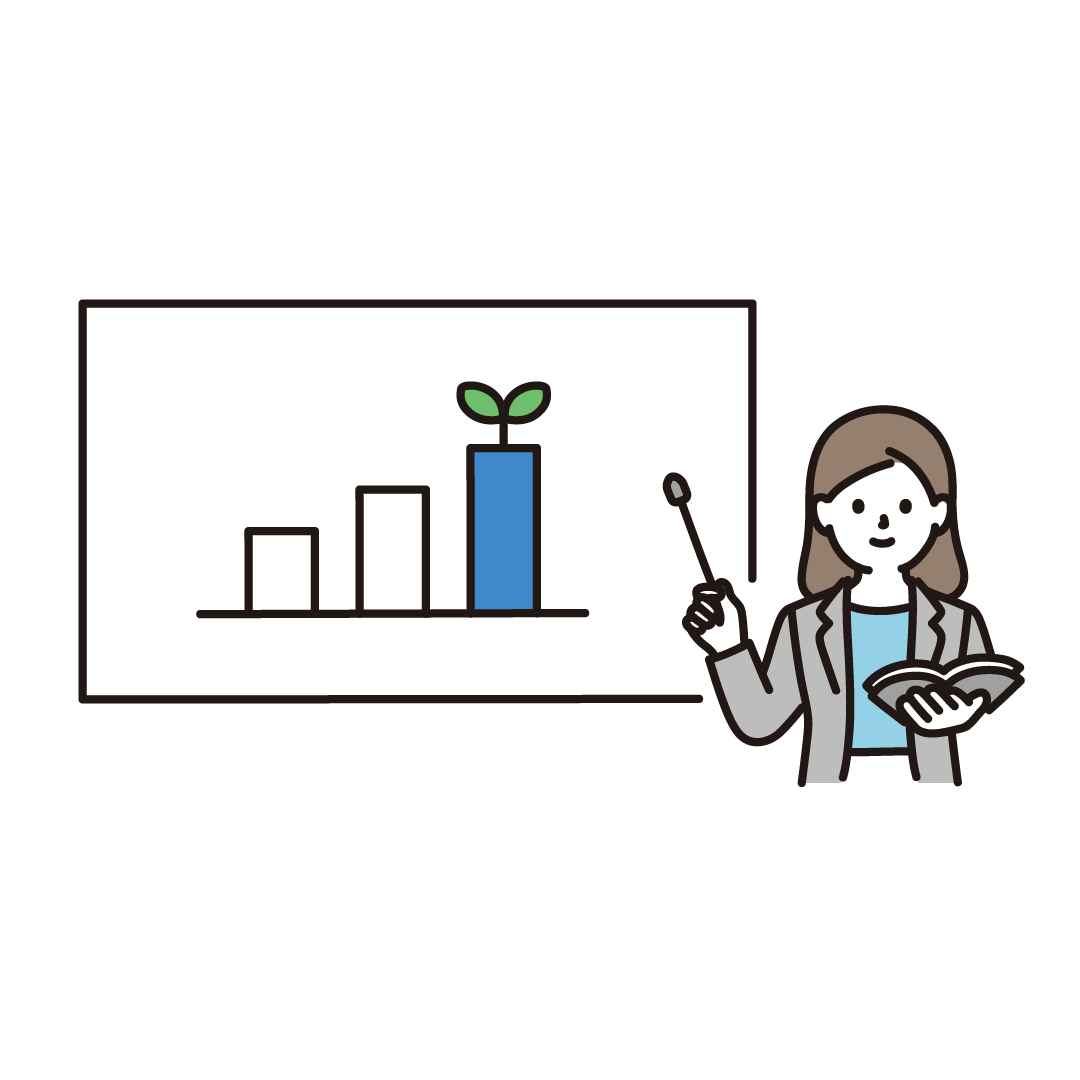
早い段階でいきなりアウトプットを結論から作るのは難しいですし、結論を作ることが出来たとしてもそれを補足するための理論を考えることに詰まってしまいかねません。
まずはマイルストーンを置いていきましょう。

例えば、新規事業がある時に「新規事業を推進すべき」という結論を伝えたい場合、「市場」「自社」「顧客」という観点・マイルストーンを置いて調査していけば論理的な説明を組み立てることが可能です。
プレゼンテーション作成では度々、「最初に空のスライドを作って言いたいことを書く」という方法がピックアップされますが、まさにこのやり方を思考全般に当てはめていく、ということになります。
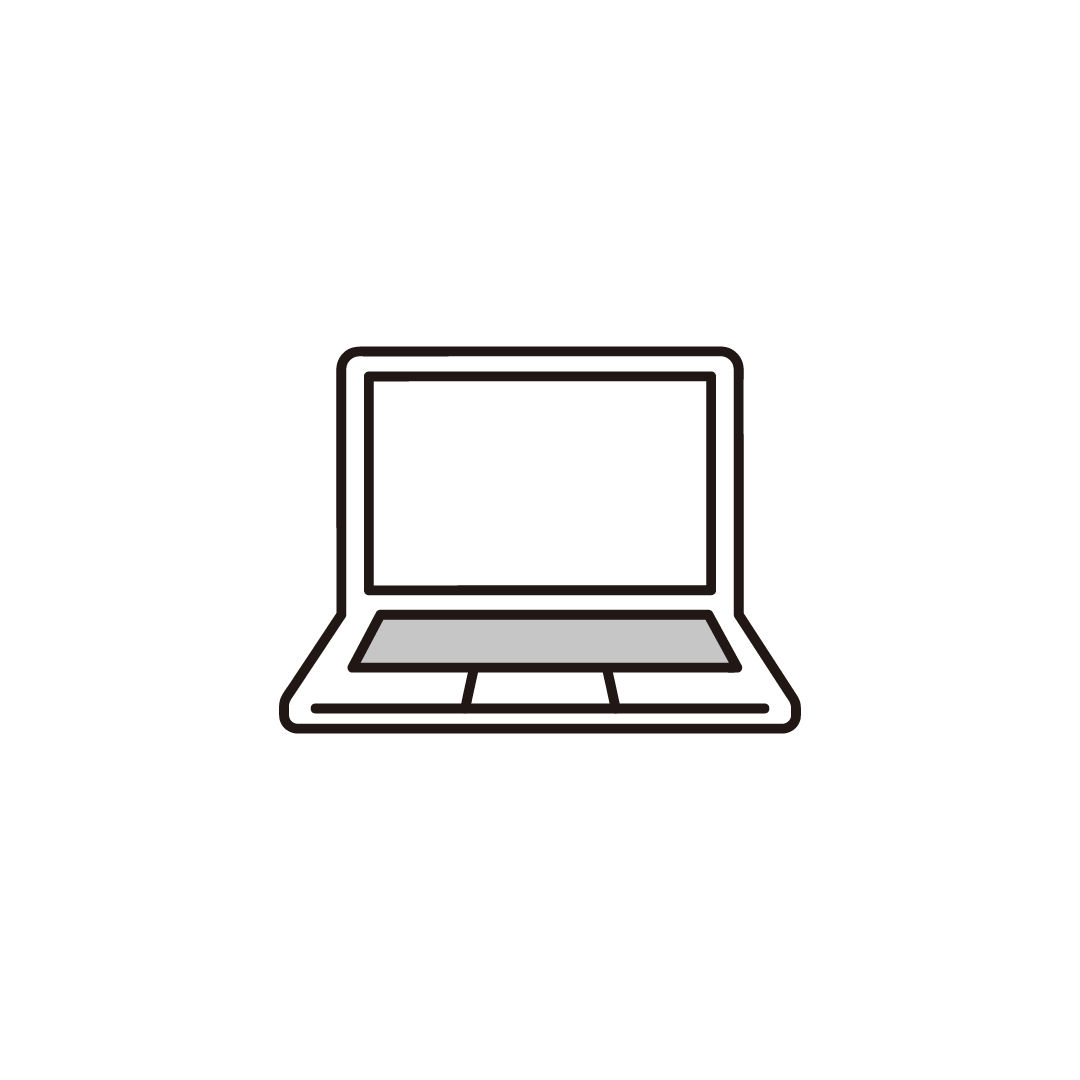
とりあえず抽象的なものを作って、徐々に具体化する。
こちらはアウトラインを作る際の考え方ですが、最初から過度に具体化しすぎる必要はないです。
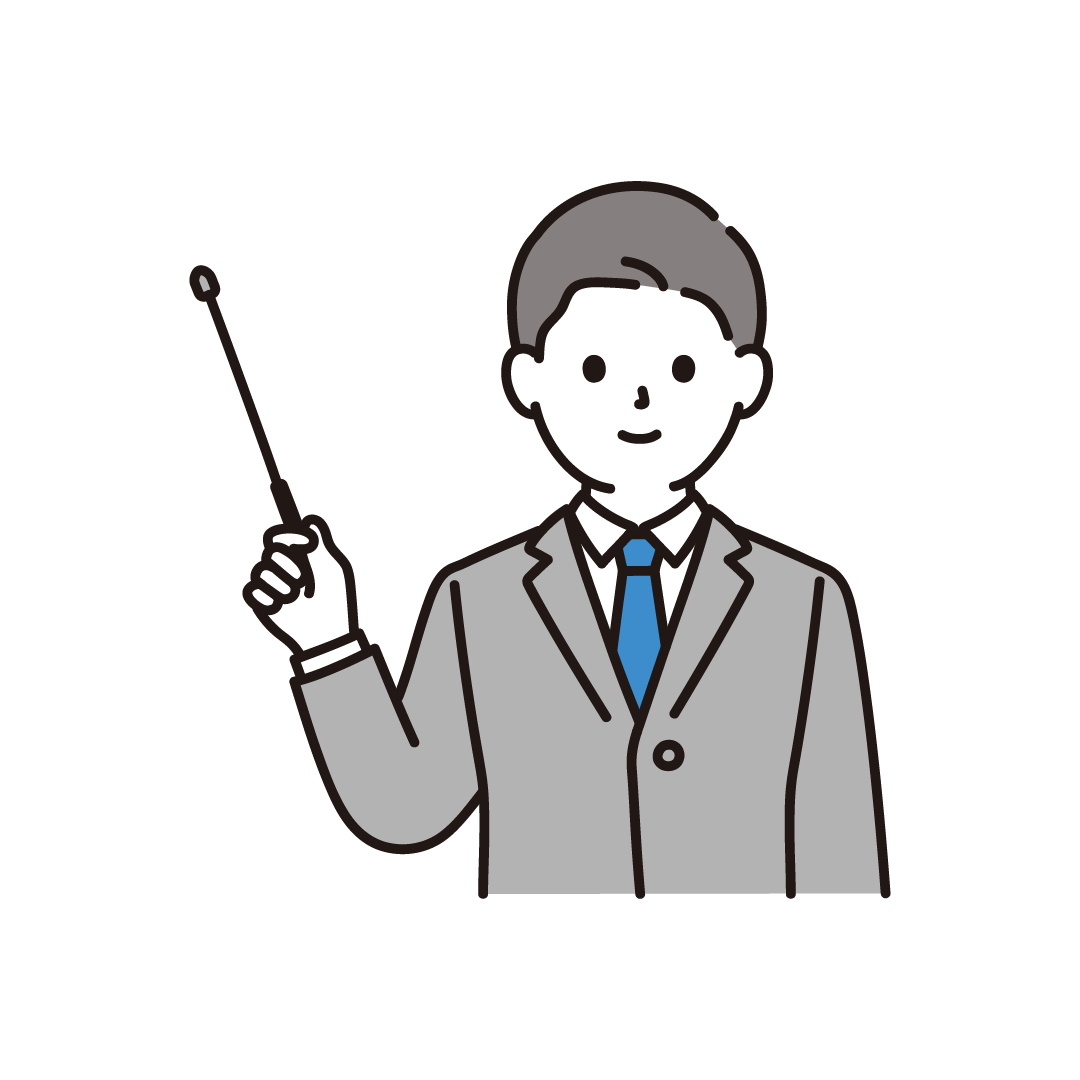
むしろ具体化しすぎない方が、後々修正しやすいですし、修正の工数も少なくて済みます。
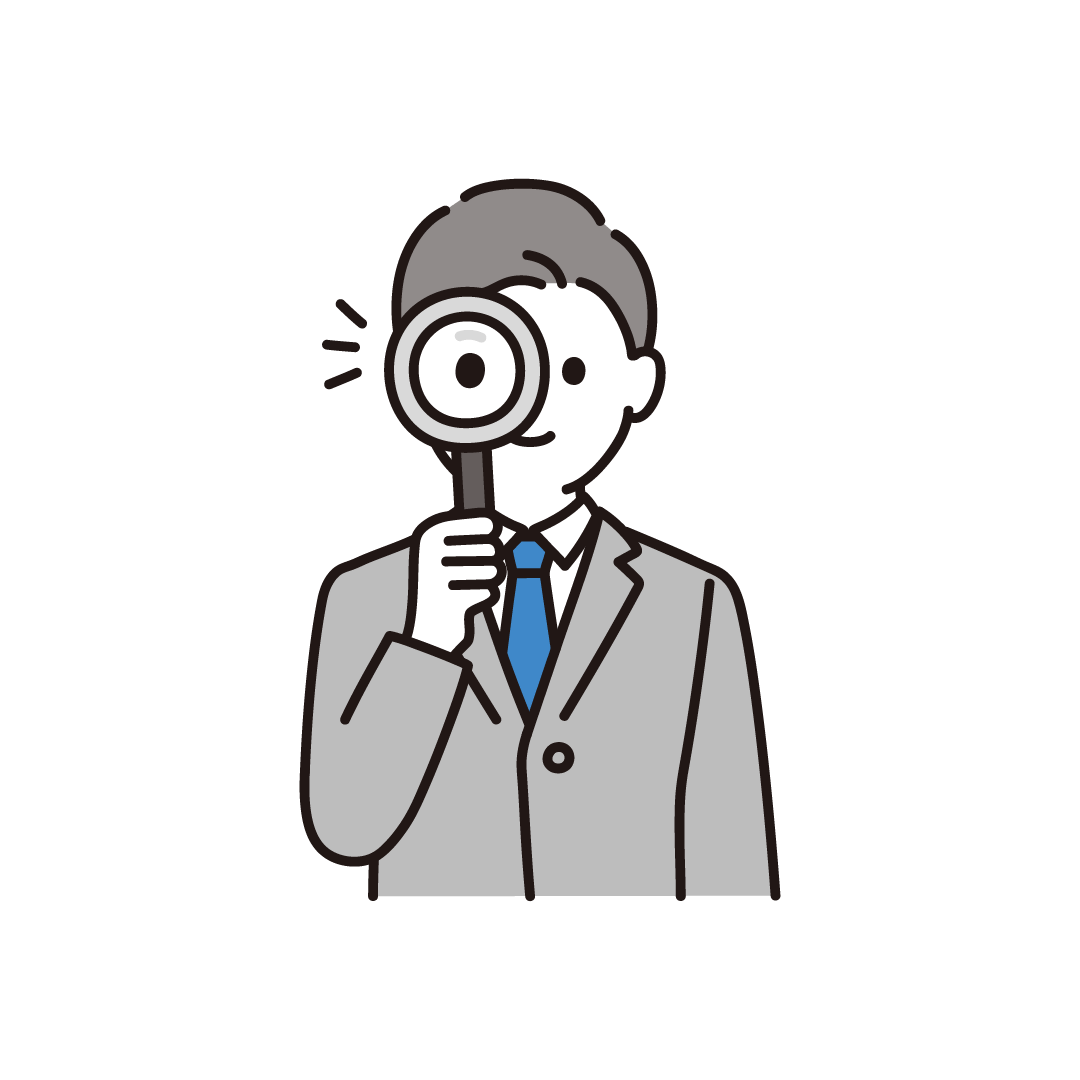
「がわ」だけ作って後から具体的にしていけばよい、という考え方を持っていると、成果物作成への取り組み方も変わるのではないでしょうか。
よく、完成度が低くてもとりあえず作ってレビューを受けるべきである、と言われますが、レビューを受けないとしても、とりあえず作るという事は重要です。
ゴールの見えないマラソンが辛いと感じるように、結論とアウトラインが見えないアウトプット作製もまた茨の道なのだと思います。
まとめ
質の高いアウトプットのために意識すべき基本的な考え方として、
①結論を決めて
②アウトラインを設定し
③抽象的でも良いので成果物を作る
の3点を挙げました。
アウトラインに沿った調査や確認によって効率的な成果物作成が実現しますので是非やってみてください。
【教養】【学習】【ルーティーン】私が新しい分野を学習する際の道標
こんにちは。
今回は学習についての話題です。
私が新しい分野を学び始める際に意識しているいくつかのことをシェアします。

始めに
何か物事を始める時、新しいことを学び始める時、難しさを感じることが多くあると思います。
新しいことを始める時にはストレスが付き物ですが、このストレスを軽減し学習を加速させるためには心の持ちようが重要であると考えています。
これからご紹介する考え方、気づきの中で何か一つでも共感していただけるのであれば幸いです。
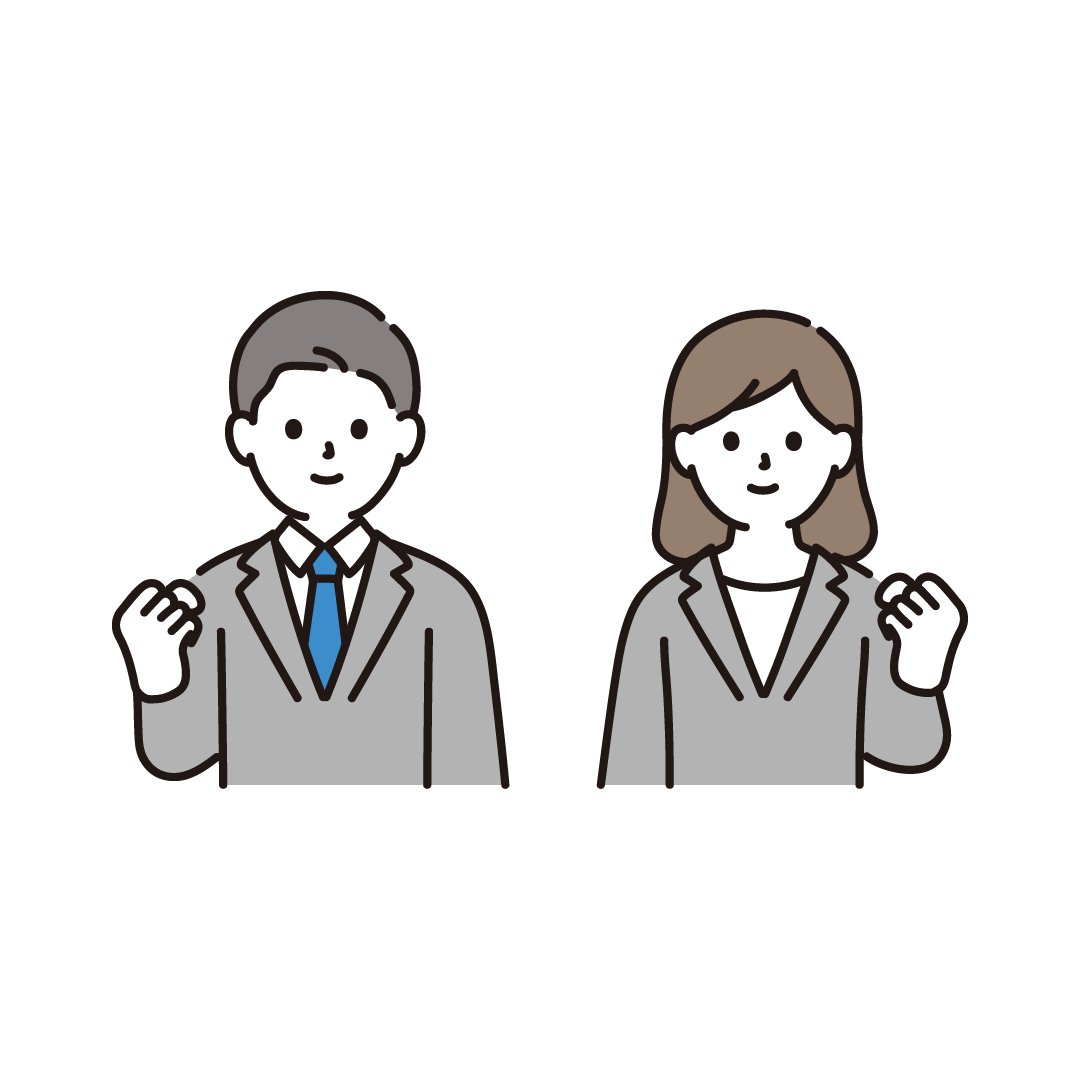
詳細
スタートダッシュの重要さを見誤るな
学習はスタートダッシュが非常に重要だ、という気づきです。

その分野における学習初期の成功体験によって、その後の成果は大きく左右されると言っても過言ではありません。
最初に行わなければいけないことは一気に完成度を上げること。
一度仕上がった学習体系は簡単には崩れない(と思っている)。
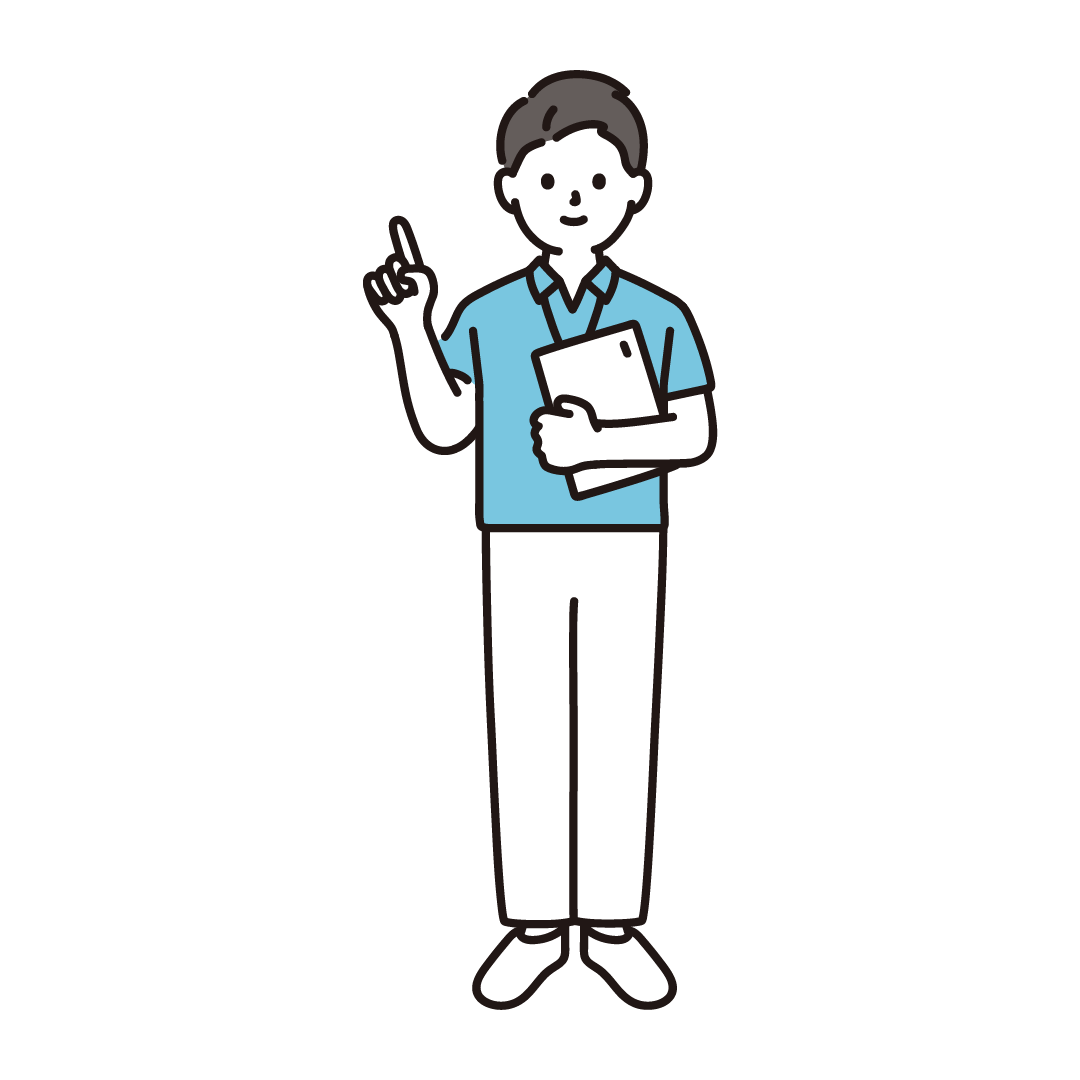
完成度を維持することは一定の負荷がかかるが、学習が進んでいないという不安から逃れる事の方が重要度が高い。
自らの要領の悪さを認識しろ
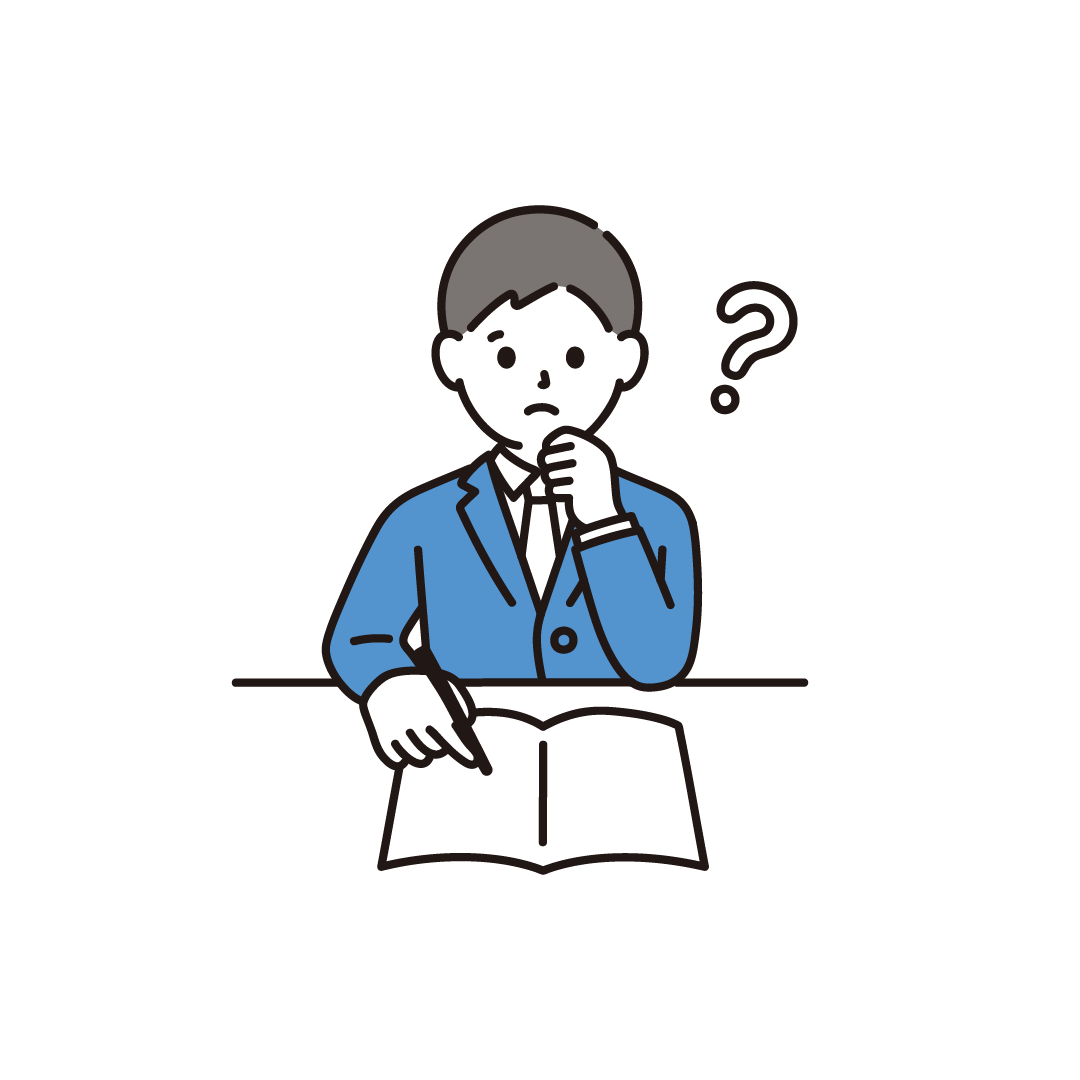
同時に複数新しいことを学ぶな、ということ。
一点突破で成果を出してから次に進むことが重要。
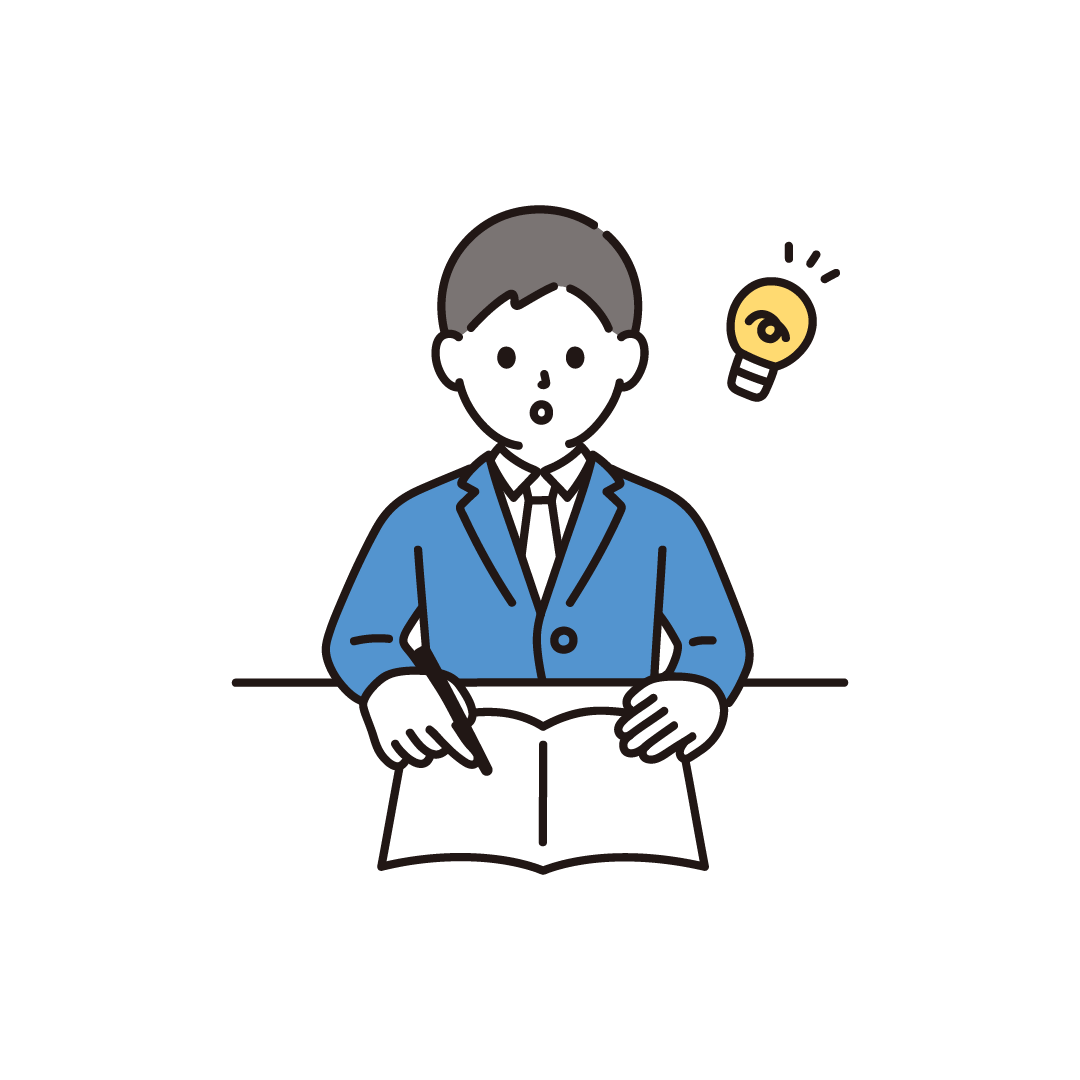
スタートダッシュを妥協するな、というメッセージを自分への戒めを込めてここに記載します。
一定の壁を越えた時に光が見える経験は誰にでもあるし、逆に言えば見えない光にすがり続けることは難しい。
成果が出ないと続けられるものも続けられないので、"新しい"ことに取り組むのであれば大量の時間を一つのものに投下するべきだという気づき。
本質の理解から目を背けるな
時間がある限り本質の理解を突き詰めるべきである、という気づき。
小手先のテクニックや単純な暗記に頼っていては身につくものも身につきません。
自身の理解度を図るにはアウトプットが重要です。
共に学ぶ仲間を作り学習範囲を説明し合う、その分野の初学者に説明して理解してもらう、等で環境を整える事も良いでしょう。
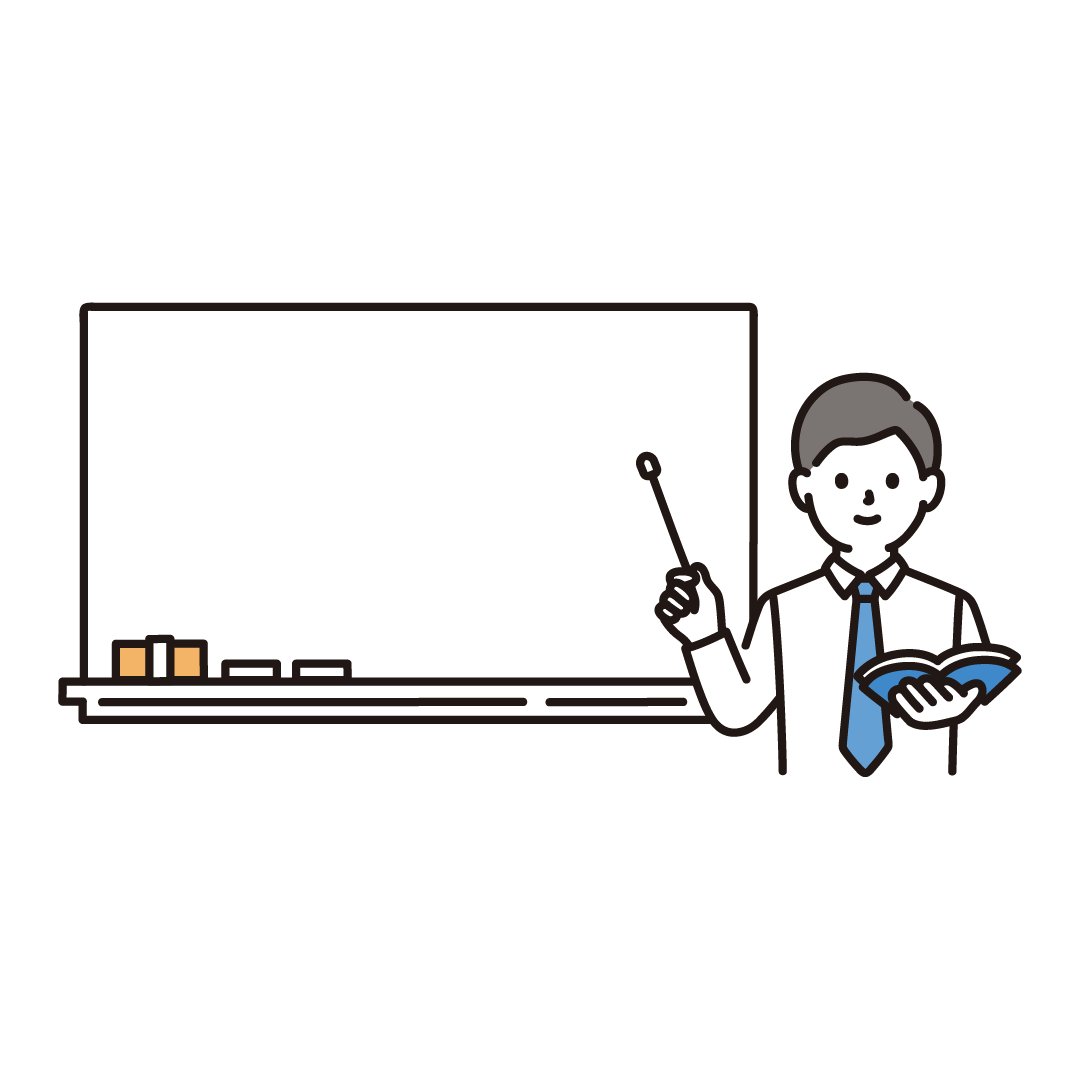
ハンズオンで学べ
机上ではなく手を動かして物事を文字通り"体感"せよ、体で覚えるというのは理にかなっている、という気づき。
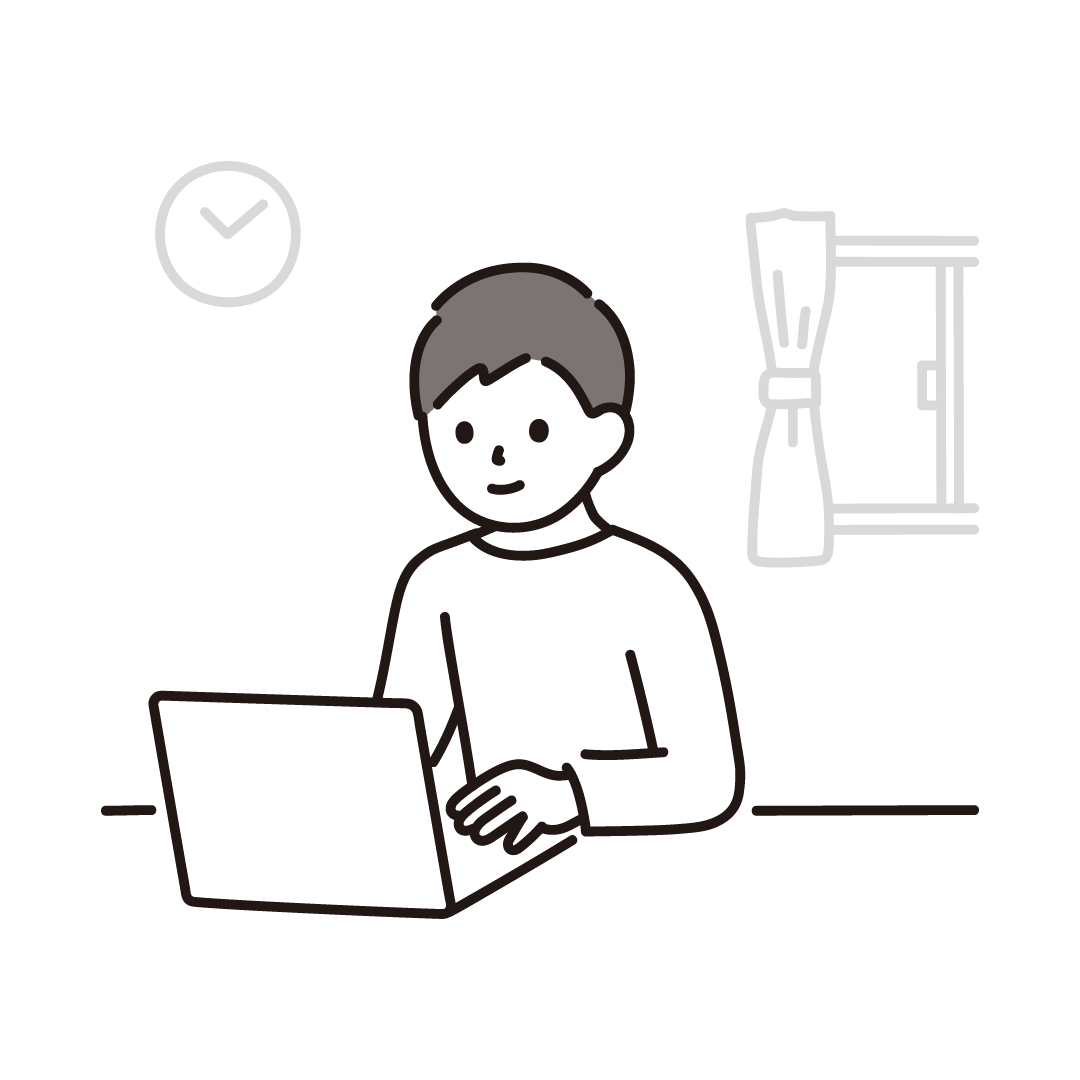
アウトプットすることが重要である、という気づきに通ずるものがありますが、理論を学ぶこと以上に実践することに拘ること重要だと感じます。
反復こそ学習の王道
無意識で動けるようになるまで同じことを繰り返し行うことが重要であるということ。

基礎・土台を作ることでその後の応用もスムーズになるという気づき。
物事を憶えるためには7回以上反復する必要がある、というのはよく言われますが、これは本当にそうだなと思います。
出来ることはより早く正確にできるように、できないことはできるようになるまで、繰り返し同じことに取り組むことで、まさに「身につく」のだと感じます。
ベンチマークを作り適度に追い込む
定期的に目標・ベンチマークを作り自身の現状を知ることが重要である。
資格試験等を受験することでその時点での自身の実力を可視化して客観的に知ることが出来るようになる。
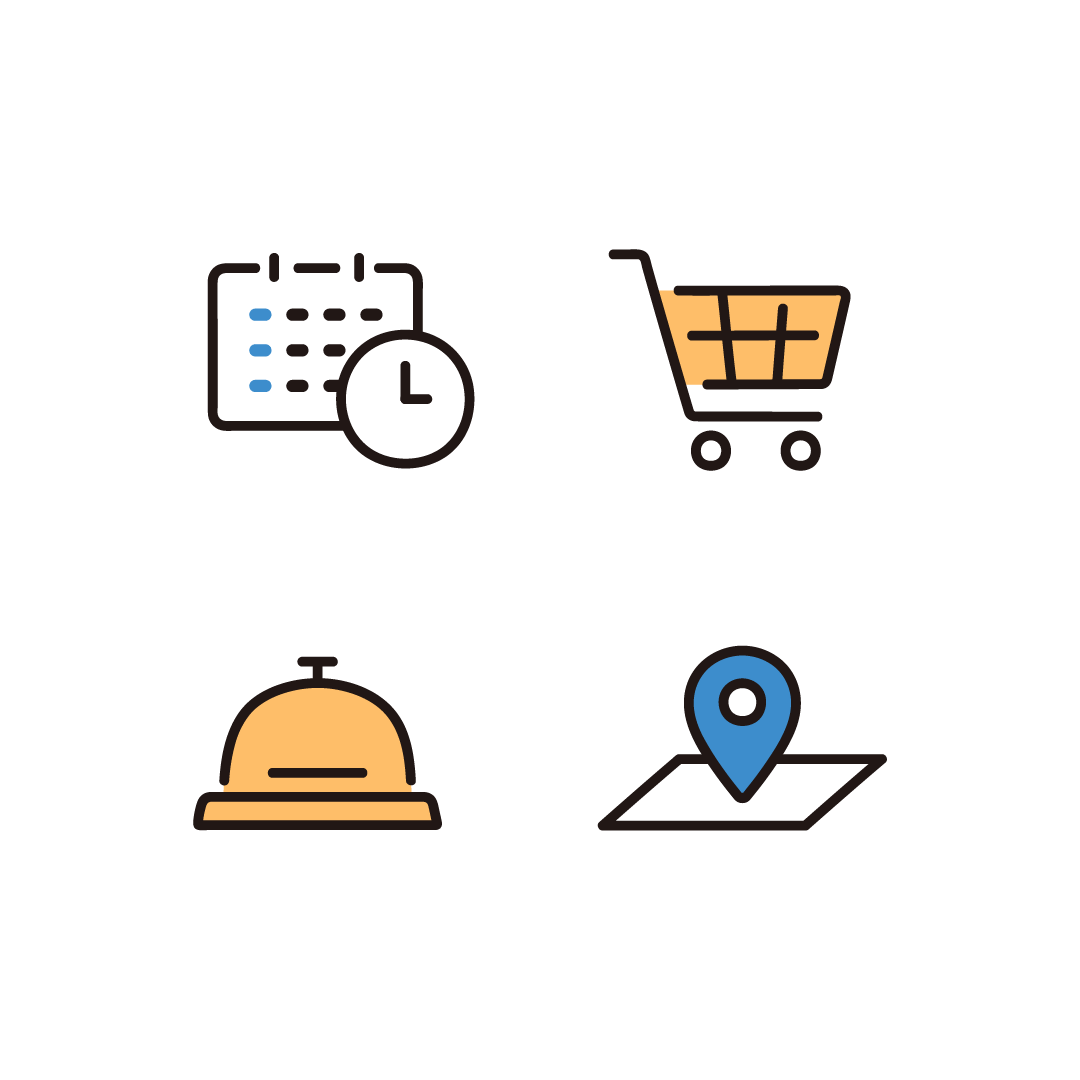
資格試験等は定期的に開催されているので定期的に受験してモチベーションを保つこともメリットの1つです。
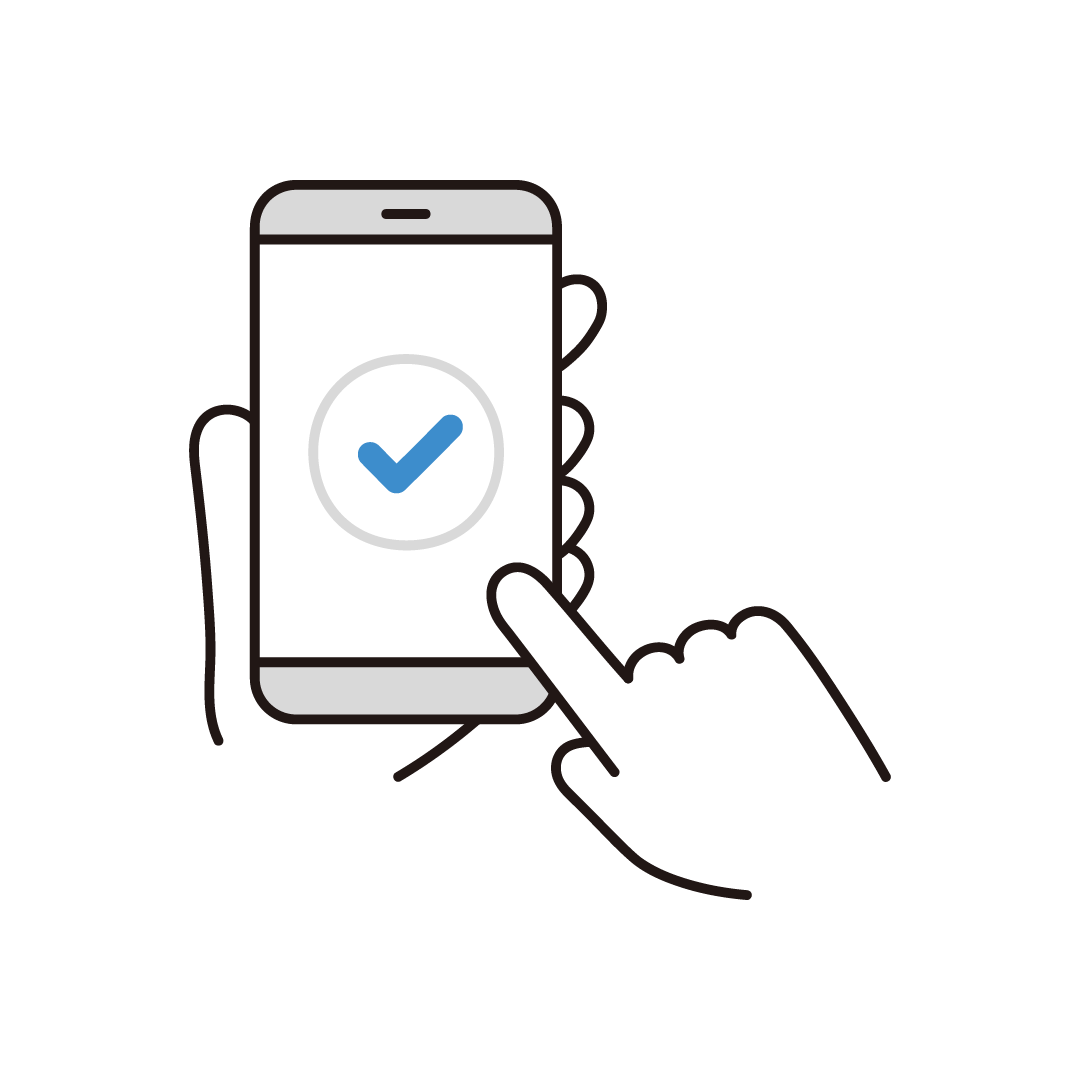
先に予定を抑えておくことで当日までモチベーションが続きますし、結果が良ければさらに良い結果のために、結果が悪ければ次回以降に巻き返しを図るために、モチベーションは続くのではないかと思います。
また、競い合えるライバルを作っておくことも重要です。
その際にはやはり、実力が拮抗していることが重要かと思います。
勿論、自身よりも学習が進んでいる相手に質問をしたり、学習が遅れている相手に理解を促したり、といったことはできますが、ライバルとしての立ち位置を考えると実良くは拮抗していた方が良いかと思います。
比較することは悪ではない
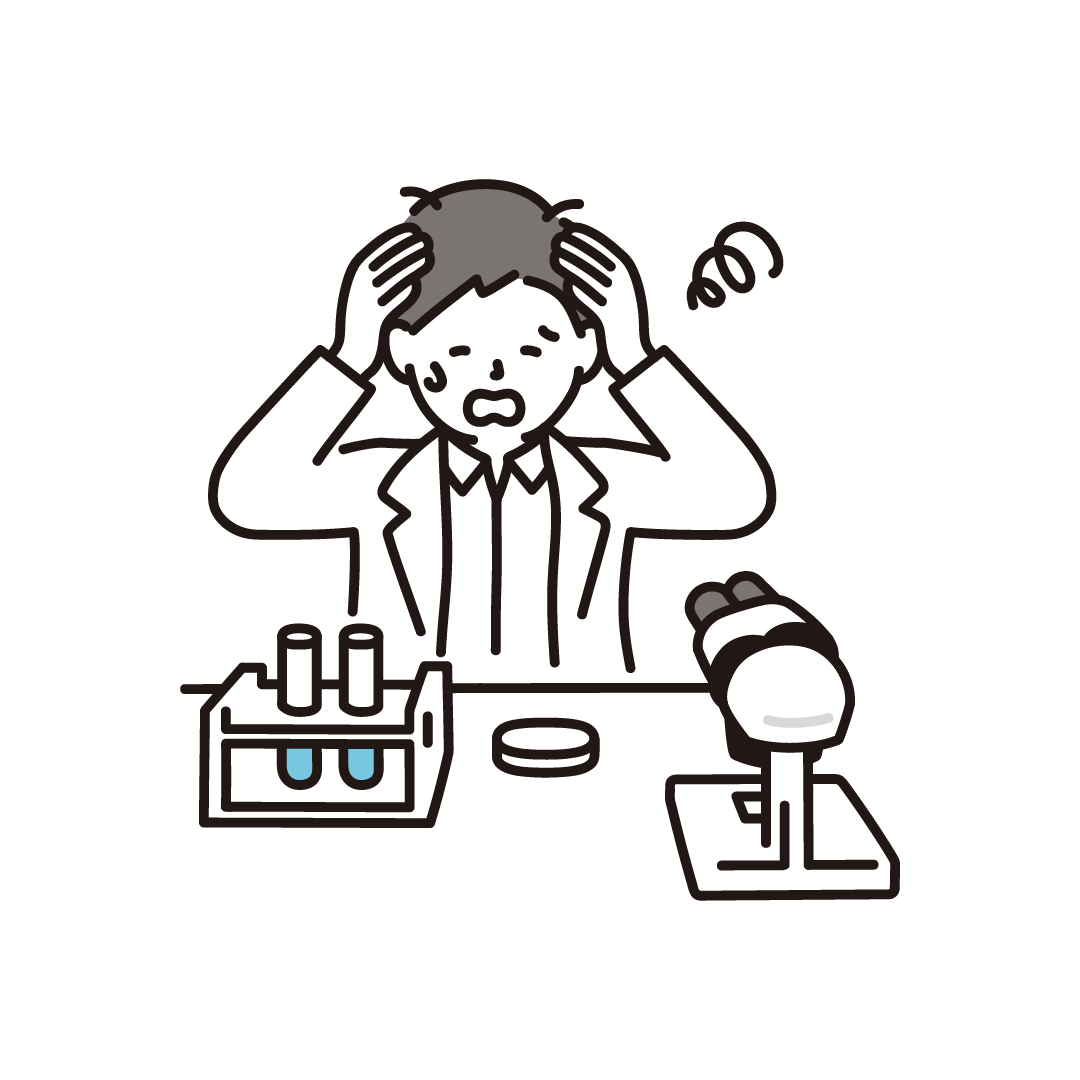
他者との比較は良いことも多い。
自身の現状の一歩外に目を向けて、外部環境と比較して差分を認識することで次のステップを踏めるのかと思います。
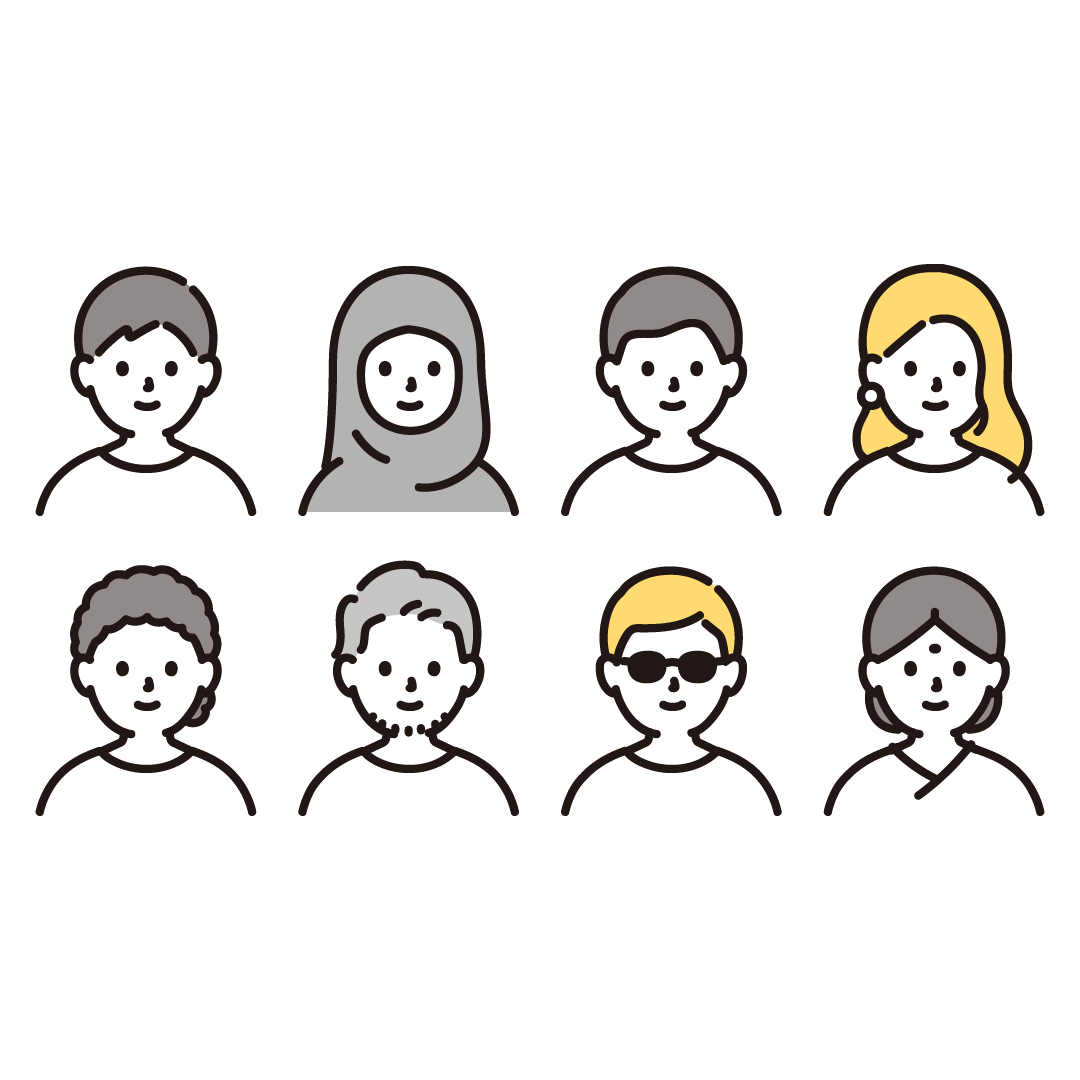
他者と差があるときに、それを埋めに行くかどうかは戦略的に判断することが重要ですし、そのような考え方に切り替えることが必要かと思います。
成果=投下時間×学習効率
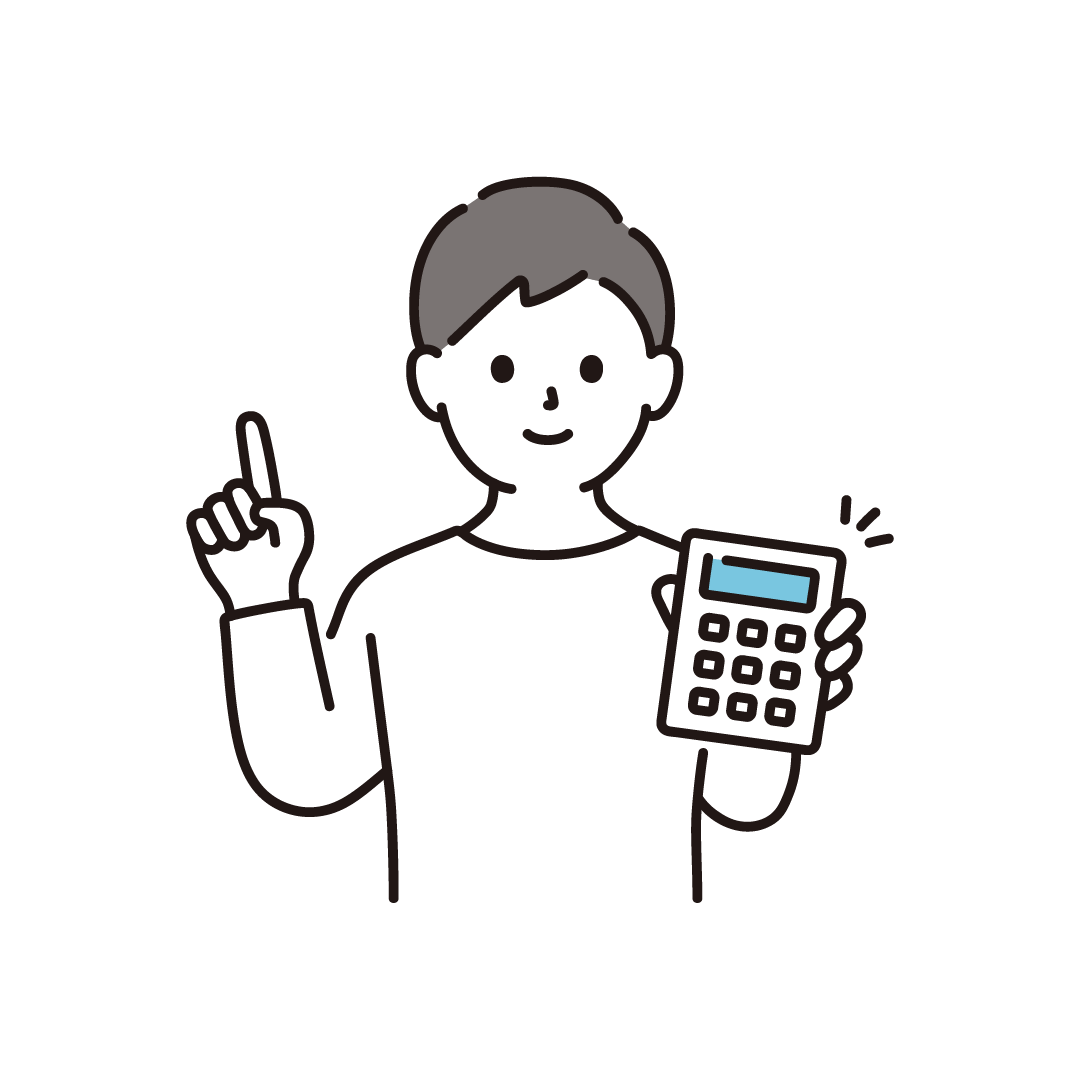
当たり前だからこそ見失ってはいけない鉄則。
成果を出すために必要な事は投下時間を増やすか学習効率を上げるかの2つに1つ。
学習開始当初は学習効率を上げる方法がわからない、となるとより多くの学習時間を投下する必要がある、という至極当然な結論を導き出すことが出来る。
勿論、一つの分野で学習を進めれば進めるほど学習効率は上がるはずなので、徐々に投下時間を減らして学習効率を上げていくことは出来るであろう。
しかし、学習効率もまた、投下時間に左右される指標になっていると言っても過言ではない。
ということで次の気づきは学習効率に対する考えである。
学習効率の数式化
学習効率=(単位時間当たり投下時間*総投下時間)/総学習時間*2
学習効率は高めるためには一定の投下時間が必要だという気づきから、総学習時間に対してどの程度の投下時間なのか、が学習効率に繋がるのではないかと考えています。
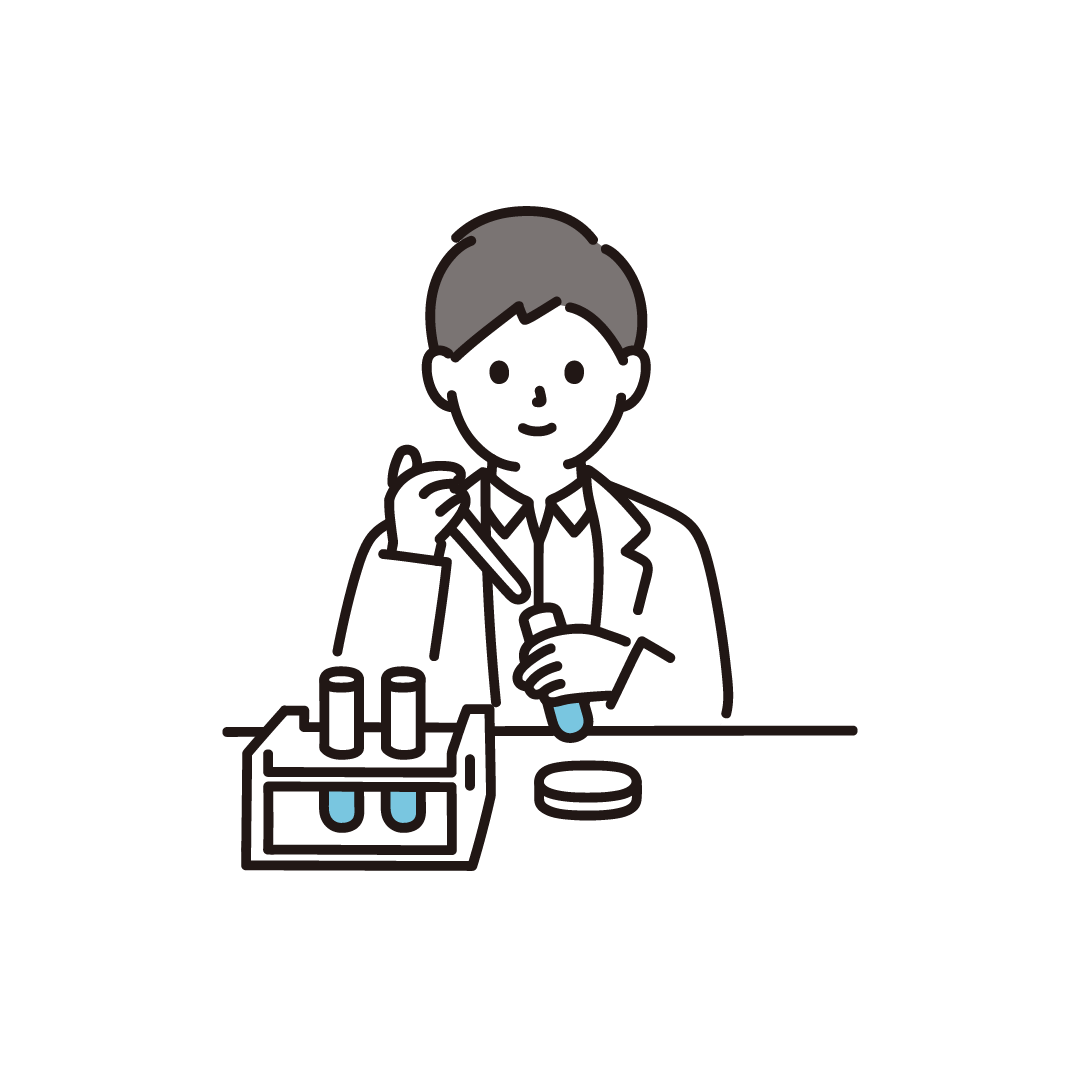
言い換えれば進捗率とも捉えることが出来る。
学習範囲全体の内のいくらかを学び終えた時に、その後の学習効率が上がるという経験があった。
最初は限りなく0に近く非常に低い効率での学習だが、学習の終盤になると理論上最大の学習効率が見えてくるのではないかと思う。
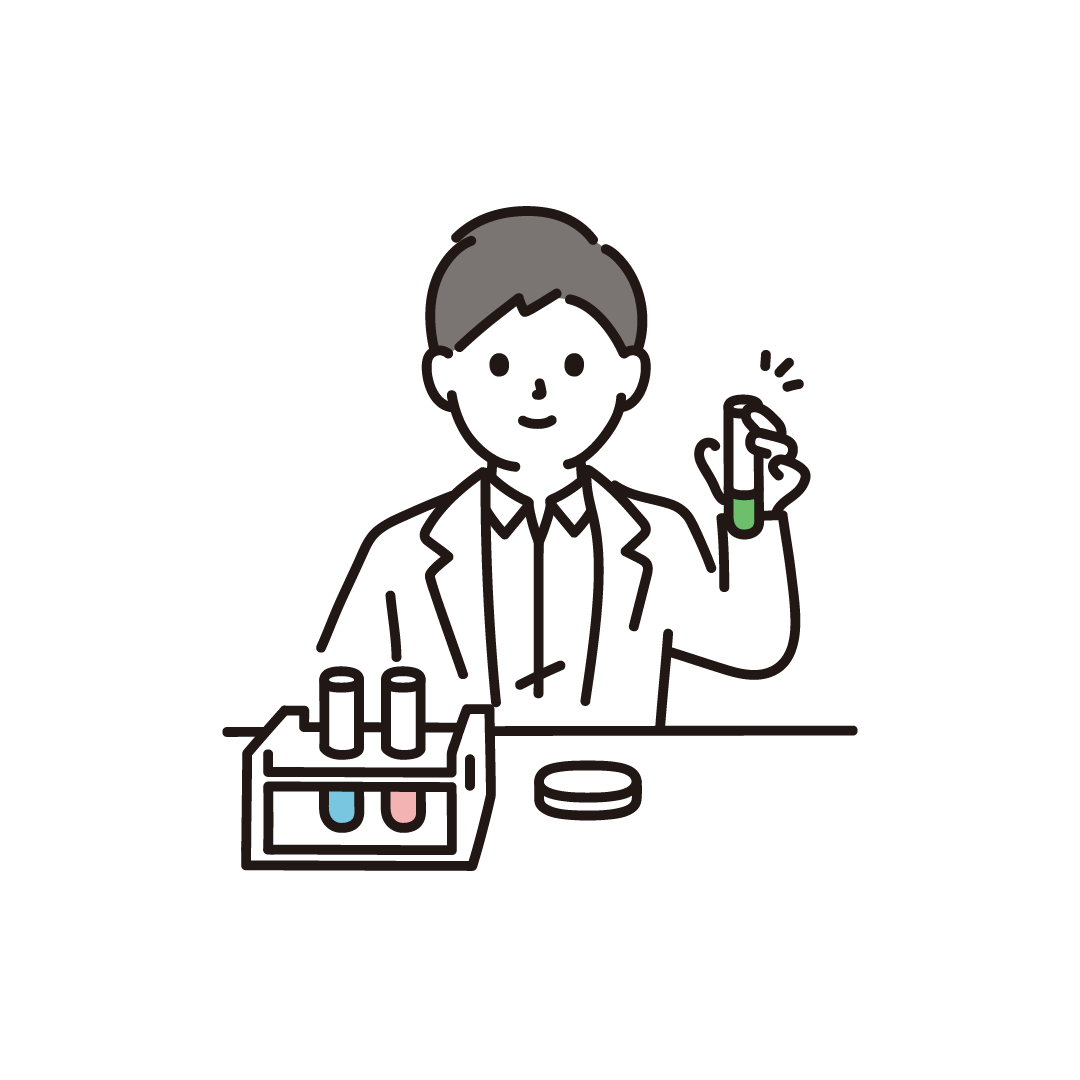
一方でだらだらと長期間勉強すればよいのか、と言うとそうではなく、単位時間当たりの投下時間を高めて学習効率を上げにいかなければいけない。
大学受験浪人生と高校生との間の学力差に関しては、学習効率の内の「単位時間当たり投下時間」の部分で説明できるのではないかと推察している。
まとめ
学習初期に投下時間を確保し集中して学習を進めることで、開始初期の成功体験を積み効率を高めたうえでその後の学習を進めていくことが重要である、という気づきです。
【思考実験】ミニマリズムとマキシマリズムに対する一つの考え
こんにちは。
今回はライフスタイル全般に対する考え方について書いていきます。
テーマはミニマリズム。
ミニマリズムへの考え方と、ミニマリズムを突き詰めるために必要なマキシマリズムについて考えていきたいと思います。
形而上学的なミニマリズム・マキシマリズムについては様々な媒体で議論されていると思いますのでそちらに譲るとして、今回は私個人へのミニマリズム・マキシマリズムの落とし込み方や考え方について、これまでの振り返りと考察をできればと思います。
ミニマリズムとマキシマリズム
ミニマリズム
ミニマリズム(英: Minimalism)は、完成度を追求するために、装飾的趣向を凝らすのではなく、むしろそれらを必要最小限まで省略する表現スタイル(様式)[1]。ミニマリスムとも表記される。「最小限主義」とも。(ミニマリズム=Wikipedia)
Wikipediaを筆頭に、必要最低限まで要素を絞ることを志向する主義・信条として定義されている「ミニマリズム」ですが、私自身もこの定義で問題ないと考えています。
1950年代には既にこの考え方に言及した文献がいくつか見られたそうですが、これまでの人類の長い歴史からするとかなり最近の考え方ということになります。
この考え方を日常生活・ライフスタイルに落としこむ際には「断捨離」などのキーワードとともに語られることがあります。
これまでの物質的充足に重きを置いた消費社会・資本主義社会へのカウンターカルチャーとして、物質への依存を脱却するべく人類が試行錯誤を施した結果として「ミニマリズム」という考え方の一部を日常で使えるデイリーでキャッチ―な表現に落とし込んだのだと思います。
比較的最近に議論が始まった「ミニマリズム」とそれらを日常生活に落とし込みデイリーユースしようとする流れから生まれた「断捨離」などの言葉から、私自身が重要視する(大半の人も日常から行っている)理解プロセスの1つである「差分理解」を行う必要があると考えている。
比較的最近出てきた言葉である「ミニマリズム」「断捨離」を理解するためには、似通った概念との差分を取るよりも両極端にある概念同士で差分を考えた方が効率的であると考え、「マキシマリズム」について考察する。
マキシマリズム
マキシマリズムについて、残念ながらWikipedia等の記述は無かったのですが、この考え方を紹介しているWeb上の記述では概して「過剰主義」「網羅的」といったキーワードと共に語られている。
こちらも特に違和感はないが、私の中ではどちらかというと「最大化主義」のようなニュアンス
提案したい考え方:ミディアミズム(mediamism)
ミニマリズムとかマキシマリズムと言った考え方・概念をこねくり回している人々の目的はと言うと、その間の最も心地良い状態・環境を見つけて身を置くことだと思っています。
その最も心地よい部分(コンフォートゾーン)を目指す考え方を仮に「ミディアミズム」と名付けましょう(検索したところミディアミズム、というものについて議論されている媒体はありませんでした。)
個々人にとってのライフスタイルの最適化については姿や形を変えて様々なところで議論されていると思いますので、今回は私自身が感じた最適化のロードマップについて書きます。
具体的には、最適化したい全ての要素に対して以下の様に経験するべきであるとかんじます。
①マキシマリズム
③ミディアミズム
これまで見てきた両極端の考え方について、マキシマリズムについては誰しもが経験するべきであると考えています。
とは言え、人それぞれ許容できる限界の過剰主義があると思いますので、節度を持って自身の必要十分なラインを探る必要があります。
何事も背伸びが必要、というのはライフスタイル全般にも当てはまる考え方であると思いますし、無理にミニマリズムを突き詰めてもそれはただの我慢になってしまいます。
自身に必要な充足感がどの程度なのかを見極めて、徐々に減らしていく過程で、真の幸福を得ることが出来ると思います。
マキシマリズムを経験する前後でミニマリズムを経験するのも良いことであると感じています。
マキシマリズムを経験する前にミニマリズムを経験することは、生活のどだいを作る上での貯金や居住地を変更する可能性を残す意味で非情に重要であると感じています。
独身であるタイミングでは就職・転職・転勤・婚約等で居住地が変わる可能性も十分に考えられます。
ここで物質的にも精神的にも身軽になっておくことは、今後の人生の選択肢を広げるうえで大きなアドバンテージになるのではないかと思います。
とは言え、精神的なミニマリズムを突き詰めすぎてしまうと、交遊関係をが狭くなってしまうなどの弊害も現れてしまいますのでほどほどにすることが大事かと思います。
また、このタイミングでミニマリズムを突き詰めておくことは「本気度」の観点からも重要です。
未だ充足された経験が無いという事は、心の持ちようによっては究極的にミニマルな蔵牛を実現できる可能性があると思います。
過度に満たされた生活を経験することによってそれ以降何事に対してもハードルが上がることはよくありますし、一度上がった生活レベルを下げることは容易ではないでしょう。
究極にミニマルな生活をした、という経験そのものが今後の生活の糧にもなりますし、いざとなればその水準まで生活レベルを下げればよい、という認識を持つことが出来るのはかなりの強みなのではないかと思います。
マキシマリズムを経験した後のミニマリズムですが、こちらも一定の効果があると思います。
自身が最大どの程度の充足で満足するか、という天井を知っている状態で最小化する作業には、自ずと優先順位が付けられるのではないかと思います。
ファッションが好きだから最低限必要な服の量は少し多いが、生活スペースは少なくても良いのでコンパクトな家を借りる。
一方でインテリアが好きだから良い家具厳選して持ちつつ、食事にはそこまでこだわらないので最低限口に合うものを自炊して外食を減らす、といった具合です。
ここでお気づきかもしれないのですが、マキシマリズムからミニマリズムへの過程でミディアミズムが訪れています。
至極当たり前ではありますが、両極端を行き来する中で中庸な点を見つけることが出来る、という考え方からすると、マキシマリズムを追い求めることが必要であると分かる。
結論
両極端の行動・考え方を実践し経験することで自分なりの最適解を導き出すことが出来るという事を意識して、何事も時には背伸びして取り組んでみようと思う。
私自身が最近感じたミディアミズム
私自身は最近、住居に関してミディアミズムへと踏み出すことが出来ているように思います。
私は現在、一般的な一人暮らしとしてはゆとりのある生活をしています。
ここで感じたこととして、「ここまで広い空間は必要ない」ということがあります。
これは勿論、家賃との兼ね合いもありますので、正確に言えば「この家賃を出してこの広さの空間に住む必要はない」という感触が正確なものになります。
今現在は引っ越ししてから日が浅いこともあって直近の住み替えは検討していませんが、契約の更新はせず2年以内で退去して「家賃を下げる」「面積を狭くする」のいずれか、または両方を行う予定です。
直近の引っ越しを通して住環境について再考する機会があり、その中で自分なりに最も快適な住環境の条件についてスコープが定まってきたと共に、快適な住環境の範囲を決めていく上で必要となる考え方についても考察することが出来ましたので、今後そのような内容についても発信していきます。